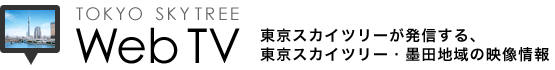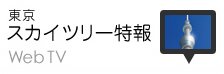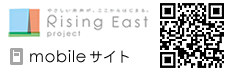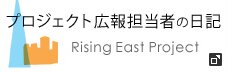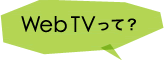明治7年(1874年)に有料の橋として民間工事により架設された厩橋(うまやばし)。元は江戸中期の元禄年間頃から続いていた御厩(おんまい)の渡しがあった場所で、名前の由来は台東区側に江戸幕府の厩舎(きゅうしゃ)が多くあったことから付けられました。
厩橋の柱には、ステンドグラスが取り付けられており、厩にちなんで疾走する馬のデザインがはめ込んであります。
蔵前橋(くらまえばし)は、関東大地震災後の復興計画で、大正13年(1924年)9月に着工し、昭和2年(1927年)11月に完成しました。ところが、橋周辺の工事が終わらなかったため、昭和5年(1930年)3月まで使用できませんでした。
橋の名前は、江戸幕府の米蔵が台東区側の隅田川沿いに多くあったことに由来して付けられたものです。橋の色は稲のもみがらをイメージさせる鮮やかな黄色。また、この橋の先に大相撲の蔵前国技館があったことから、橋の欄干には力士のレリーフがデザインされています。